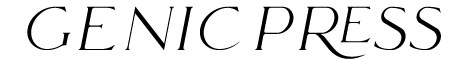受賞の秘訣は「ロボコン」だって!学生がチームで協力し合いながら学ぶ様子が注目されたんだ。これはマジで面白い試みだよね🤖🛠️
解説
岡山理科大学が「第29回工学教育賞」を受賞しました!🎉これは、ロボットコンテストを通じて学生の成長を促す素晴らしい取り組みが評価された結果です。この教育手法は、ただの技術教育ではなく、「前に踏み出す力」や「考え抜く力」、「チームで働く力」といった、企業が求める基礎力を育成することを目的としています。学生は仲間と協力しながら解決策を見出し、負けずに挑戦することで数々の成長を体感しています🚀⭐️。赤木教授は、現在もIoTやAIを取り入れた新たな教育内容を模索しているとのこと。まさに未来のエンジニアを育成する環境が整えられていると言えるでしょう!
この記事のポイント!
1. ロボコンを通じた実践的な教育方法
2. 社会人基礎力の育成に特化
3. 長い歴史を持つ教育手法
4. チームワーク重視のカリキュラム
5. IoTやAIを取り入れた最新教育

代表者の赤木徹也教授によると、この取り組みは、「企業が喉から手が出るほど欲しがるエンジニアを育成」するために、学部(2021年度までは工学部知能機械工学科、2022年度より情報理工学部情報理工学科)の3分の1以上の教員が20年近く関わってきた実践的なものづくり教育。1年生は全員が受講し、2、3年生は専門コースの学生が優先されるものの、希望すれば学部の学生全員が受講できるカリキュラムです。
その内容は、入学間もない1年生が知らない者同士でチームを組み、勉強しながらロボットを製作して、コンテストに挑戦することで、まずは「チャレンジすることへの意識改革」を行います。2年次、3年次では、競技の順位はもちろんのこと、直面するトラブルを解決して締切(納期)に間に合わせるために、如何に皆と協力していくか、という創造的な競争活動にも取り組みます。締切(納期)に間に合わず悔しい思いをすることも、学生たちにとっては成長の糧になります。
1年次、2年次で失敗したとしても再チャレンジできるよう、講義は体系的に構成されています。このロボコン教育を受けた学生が筆頭著者として執筆した論文の投稿率や国際会議での発表率が6倍に増えるなど、顕著な効果も出ているそうです。
赤木教授は「長年取り組んできた教育手法が評価されて本当にうれしいです」と受賞の感想を述べ、「経費も手間もかかりますが、この教育を受けた学生に対する評価は高く、ロボコンをガクチカ(学生時代に力を入れた事)とすると、企業の人との話が弾んだと喜ぶ学生も多いと聞いています」と成果を強調。教育内容については「IoT(情報通信技術)やAI(人工知能)などを取り入れたロボコンの設定など、時代に合わせた課題も模索しているところです」と話しています。