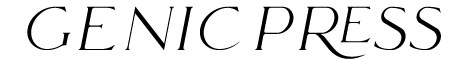熊本産の大見柑を使った、「寶CRAFT」クラフトチューハイ。美味しさとエコを両立した商品が新登場!🍹
解説
「寶CRAFT」熊本大見柑は、地域限定のクラフトチューハイで、地元の素材を最大限活かした特別な製品です。果汁だけでなく、果皮からも香りを抽出し、味わいの深さを実現しつつ、約30%の廃棄ロス削減を達成しています✨。この商品は、熊本県宇城市で採れた「大見柑」を使用していて、酸味と甘みのバランスが絶妙で、特に地元名物の「馬刺し」との相性が抜群です!😄また、見た目にも新鮮なラベルデザインを採用し、楽しさを引き立てています。フレッシュな味わいをぜひお楽しみください!🍹
この記事のポイント!
1. 熊本県の大見柑を使用したクラフトチューハイ
2. 厳選した樽貯蔵熟成焼酎を使用
3. 廃棄ロスを約30%削減
4. 地元名物、馬刺しとの相性抜群
5. フレッシュ感あふれるラベルデザイン

“「寶CRAFT」”は、日本各地のご当地素材を使用し、それらの個性を活かし、厳選した樽貯蔵熟成焼酎をあわせる「ひとてま造り」製法で丁寧に仕込んだクラフトチューハイです。現在までに、42アイテム※1をラインアップしています。
「大見柑」は、熊本県宇城市(うきし)不知火町(しらぬいちょう)大見(おおみ)で採れた不知火(柑橘類)※2です。
今回新発売する“「寶CRAFT」<熊本大見柑>”は、「大見柑」の爽やかな酸味と程よい甘みが楽しめるクラフトチューハイです。熊本県のご当地グルメ「馬刺し」にもよくあいます。果汁だけではなく、搾汁後本来なら廃棄されることの多い果皮からも香りや味わい成分(オイル)を抽出して使用することで、果汁だけでは表現することのできない、果実の複雑さや深みを表現しました。また、果汁だけを使用した時と比べて約30%の廃棄ロス削減にもつながっています。
不知火は通常、年末から1月にかけて収穫され、酸味を落とすために2カ月程の貯蔵期間を経てから市場に出回りますが、貯蔵過程で青果が腐敗し、出荷できず廃棄されるものが年間20%~最大50%あります。
本商品で使用する「大見柑」は、通常よりも早い時期に収穫を行い、貯蔵期間を経ずにチューハイの原料に加工することで、廃棄ロスを年間約1%にまで削減することができました。また、早い時期の収穫により、木の負担軽減※3や生産者の繁忙期分散にも貢献しています。

今回新発売する“「寶CRAFT」<熊本大見柑>”は、「大見柑」の爽やかな酸味と程よい甘みが楽しめるクラフトチューハイです。熊本県のご当地グルメ「馬刺し」にもよくあいます。果汁だけではなく、搾汁後本来なら廃棄されることの多い果皮からも香りや味わい成分(オイル)を抽出して使用することで、果汁だけでは表現することのできない、果実の複雑さや深みを表現しました。また、果汁だけを使用した時と比べて約30%の廃棄ロス削減にもつながっています。
本商品で使用する「大見柑」は、通常よりも早い時期に収穫を行い、貯蔵期間を経ずにチューハイの原料に加工することで、廃棄ロスを年間約1%にまで削減することができました。また、早い時期の収穫により、木の負担軽減※3や生産者の繁忙期分散にも貢献しています。
当社は、日本各地で丁寧に育てられたご当地素材を活用したクラフトチューハイの発売・育成を通じて産地を応援するとともに、これからも確かな技術で「和酒」の新たな美味しさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。

「大見柑」の味わいをイメージしやすいように、ラベル中央に果実のイラストをあしらい、フレッシュ感のあるカラーリングと果実の弾けるようなみずみずしさをドットで表現しました。加えて、熊本県を想起させるイラスト(阿蘇山、熊本城、天草五橋、熊本県地図)を配置。天草地域で有名なイルカウォッチングを表現するために“隠れイルカ”をデザインした点もこだわりのポイントです。
【商品概要】
商品名:「寶CRAFT」<熊本大見柑>
品目:リキュール(発泡性)
アルコール分:8%
果汁分:1.5%
純アルコール量:1本あたり21g
容量/容器:330ml/壜
梱包:12本段ボール箱入
参考小売価格(消費税抜き):320円
販売地域:熊本県を中心に販売
発売日:2025年4月15日(火)
【参考】“寶CRAFT”ブランドサイト
https://www.takarashuzo.co.jp/products/soft_alcohol/takara_craft/
※2 不知火:清見オレンジとポンカンをかけ合わせた品種で、大見柑を含む果実の総称 大見柑:熊本県宇城市不知火町大見で採れた不知火
※3 柑橘類は品種ごとに樹勢(樹木の生育状況や成長の勢い)が異なる。また、多くの柑橘類は春から初夏にかけて開花し結実するが、果実の収穫時期は品種によって異なる。不知火は他の柑橘類と比較し、樹勢が弱いにも関わらず、結実から収穫までの期間が長い。収穫時期を早めることで、木が果実に養分を送る際にかかる負担やエネルギーの消費を軽減し、木の健康を保つことが、持続可能な果実生産にも繋がる。