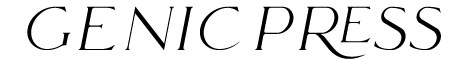今回の訓練は、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震発生から6年目を迎える時期に、大規模地震が発生した際、児童生徒の安全を確保するため教職員の動きが定められた危機管理マニュアルに沿って行う事で、教職員の危機発生時対応力向上を図ることを目的に企画されました。訓練は、事前にシナリオが知らされない「ブラインド訓練」の方式で、訓練参加者が教職員役と児童役とに分かれ、SPS認証校で勤務する学校安全推進責任者が与える状況付与の指示に基づいて、地震発生時の対応を実践。市立小学校など45校から約120人の教職員が参加し、実際に行動してみて気づく課題点などについて、確認を行いました。
訓練では、学校の昼休みに大規模な地震(震度6強の本震、震度5強の余震)が発生し、教室、トイレ、運動場などで休み時間を過ごしていた子どもたちが、「揺れの恐怖で動けない」「パニックになってトイレの個室から出ることができない」「地震で足を負傷し自力で歩行できない」などを想定した状況付与に対し、教職員役を務める訓練参加者が、危機管理マニュアルに基づき対応を実践。負傷した子どもをタンカで避難場所となる運動場へ搬送する訓練や逃げ遅れた子どもがいないか確認場所を分担しながら校内を捜索するなどの対応を行いました。その後、参加者はグループに分かれて訓練の振り返るとともに、マニュアルの改善点について意見交換。参加者からは「子どもたちの安全を守るため、非常時には担任する学年が違う先生間の連携をスムーズにすることが大切だ」「地震発生時に屋外にいても不安になり校舎内に戻ってくるケースも想定されるので屋外の子どもへ声掛けをする職員を配置する必要がある」などの意見がありました。
【参考情報】
■
高槻市教育委員会における学校安全の強化に向けた取り組みの経緯
高槻市では、安全管理に対する体制の再構築を図るため、令和元年に「学校安全対策について(指針)」を改訂し、「全ての児童生徒等が、安全に関する資質・能力を身に付けること」を学校安全のめざすべき姿の一つとして設定し、その実現に向け、学校安全の3領域「生活安全」「交通安全」「災害安全」を網羅し、年間計画の策定や活動の実践、評価、課題への対応・改善等を行う「セーフティプロモーションスクール(SPS)」の認証取得を進めてきました。寿栄小学校が令和3年3月に、第三中学校・芝生小学校・丸橋小学校が令和5年2月にSPSの認証を受け、第三中学校区の全ての小中学校がSPSの認証校となりました。現在は、これまでにSPSの認証取得に向け蓄積してきた第三中学校区の取組成果を他校に普及させ、全市的な学校安全の質の向上と一層の推進を図っていくための取り組みを進めているところです。
■
学校安全推進責任者とは
本市では、安全教育・安全管理・組織活動といった学校安全に関する組織的取組を推進するために、各学校における学校安全の中核を担う教職員を「学校安全推進責任者」として位置付けています。
■
ブラインド訓練について
ブラインド訓練とは、参加する職員(実施校含む)に対してシナリオが伝えられずに行う訓練です。発生した状況に応じて、自校の危機管理マニュアルに沿った対応が臨機応変に実施できるか、また訓練を経て自校の危機管理マニュアルの内容の改善点について実感を持った検証ができる機会として、本市ではこうした実践的な避難訓練の取組を推進しています。