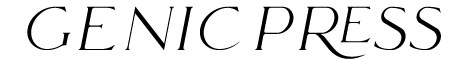コートヤードHIROOにて、6月14日(金)より窪田望、丹原健翔による二人展「RHODA」を開催いたします。人工知能は人類の生活に効率化をもたらし、我々の日常生活そしてアート界においても確実に身近な存在になっていると言えます。人工知能と人類との関係性を見つめるとき、そこから見えてくるものは何か。AI開発者でもある窪田と現代人のナラティブをテーマにしてきた丹原氏による展示を是非この機会にご高覧ください。

会 期 : 2024年6月14日(金)~6月30日(日)
会 場 : コートヤードHIROO ガロウ (〒106-0031東京都港区⻄麻布 4-21-2)
時 間 : 12:00 〜 19:00 ※初日、6月14日(金)は19:00オープンとなります
休廊日 : 月曜日
入場無料
■Opening Party:
2024年6月14日(金) 19:00~<入退場自由・予約不要>
■Talk Session
【会場参加・限定30名様 / オンライン配信 】
日 時:2024年6月23日(日)17:00~<要予約>
会 場 : コートヤードHIROO ラウンジ 〒106-0031東京都港区⻄麻布 4-21-2
※オンライン参加の皆様 配信URL等をイベント前にご案内をさせていただきます
参加申込▶
https://rhoda0623.peatix.com/
1950年代の戦後アメリカ。経済がこれまで以上に加速化し、ベビーブーマーがこれからのアメリカをより自由で強固な国にしてくれると期待されているなか、ウィリアム・マーチによる小説『悪い種子』(原題:The Bad Seed、1954年)は大きく話題となった。Enfant Terrible=恐るべき子供たちとも称されるホラージャンルの先駆けで、殺人を犯す8歳の少女と、連続殺人犯だった祖母から続く遺伝の呪いを題材にしたサスペンス本作は、出版後2年も待たずに舞台化・映画化がされた。ストーリーについて特筆すべきは、主人公であるローダ(Rhoda)が殺人を繰り返す姿に、実は祖母が伝説の連続殺人犯であったことが中盤でわかることで、視聴者が強引にも「納得」させられるところである。「蛙の子は蛙」というのが一つのアンサーになり、一瞬にしてサスペンスミステリーから、確かな敵意と対峙するホラー映画に変わる。ローダの母は、セラピストに子育て次第で子どもは変わると言われ安堵をするも、まもなくその犯罪の全貌がわかり、遺伝という呪いに抗えない絶望で自殺する。
この演劇と映画が話題となった1950年代では世界中で戦争の爪痕としての孤児院が多く建ち、その施設に住む”特異な”子どもたちはしばし研究対象となった。現代の子育て論に大きく関与する精神科医のボウルビィの愛着理論(1951に初めて言及)をはじめ、子育てに関する研究が多くなされた時代である。信仰と権力が定めてきた従来の子育て論を刷新した、Empirical(経験主義的)で論理的な体系への試みが一般の子育て世代に広まる最中、『悪い種子』は実に残酷で恐ろしい映画に見えただろう。戦争という罪の数々に、後天的に抗うことができないのかもしれないという絶望。繰り返してはいけないと誰しもが多かれ少なかれ思っているその意識を、逆なでするようであった。実際、映画版では当時の観客への配慮と映画倫理規定によって、結末に殺人鬼ローダに突然カミナリが落ちて死ぬ「ハッピーエンド」が加えられた。
2020年代。人工知能の”暴走”を恐れ、法整備やルールの制定が急がれる。AIを”悪用”することを防ごうと世界中の巨大企業や政府が動き、我々はその存在を擬人化して扱う。「より人間的」に受け答えのできるチャット、ディープフェイクなどの技術によって生成される「より自然な人物像」、アーティストを模倣した「より本物っぽいAIアート」など、度々熱論が交わされる話題が流行る。そのたびに、世界世論は騒ぎ、現代美術は問題提起を急ごうと制作される。不可逆なシンギュラリティの瞬間に向けて、我々は安心のインフラストラクチャを求めざるを得ないのである。そうして”悪用”されない、つまり”正しい”人工知能の使われ方を求める中で、我々一人ひとりの中で定めている”正しさ”が暴露されるのである。人工知能の学習に扱っていいデータを規制し、活用に関してルールを定め、AIを人類が”育て”ようとすることは、我々の考える”正しさ”との対峙そのものだろう。
それは、AIというものが膨大にも、あくまで既存のデータから学習して出力しているというわけだから、当然といえば当然である。自明的とも見えるからこそ、側面として絶望的な恐怖を備えている。昨今でも絶えない争いの数々を観ていて考える。もしも、人工知能によって世の中の数多ある問題が何一つ解決しなかったら。悪用そのものではなく、ただただ繰り返される、人類が抱えてきた罪の継承の現れ。そういったものを、僕たちは恐れるのである。
丹原健翔

窪田望 NOZOMU Kubota
経営者、AI開発者、発明家、YouTuber、美術家とジャンルを横断しながら、表現を行う。東京藝術大学大学院先端藝術表現、修士課程。AIの特許を日本・アメリカ・中国・香港で20個発明し、YouTube、TikTok、Xの総フォロアー数は30万人おり、自動運転の分野ではGoogleの精度・頑健性を上回る数値を出力するAIを作るなど、AIやデジタルを使った表現が得意。 2022年から現代美術の分野で作品制作を開始。
Ginza Six、資生堂パーラーで生成AIを用いた動画作品や半透明タペストリー作品を発表する他、ChatGPT、そしてフィジカルな装置を組み合 わせたインタラクティブな作品を制作し、また 山形県西川町では消えつつある方言をAIに学習 させるなど、メディアテクノロジーとコンセプチュアルな手法を駆使し人間とAIというありふれた二項対立からの脱構築の実践を試みる。

丹原健翔 KENSHO Tambara
作家、キュレーター。現代におけるコミュニティの通過儀礼や儀式についてパフォーマンスを中心にボストンで作家活動をしたのち、17年に帰国、国内で作家・キュレーターとして活動。サイトスペシフィックな作品や展示をつくることを中心に、鑑賞者のまなざしの変化を誘発することを目的に制作。
写真:野本ビキトル(METACRAFT)提供:e-vela.jp
展示作品(一部)のご紹介
展⽰作品①:Massive Ugly Hands (制作:窪田望)


ミシェル・フーコーの《狂気の歴史》では癩病患者が社会的にも物理的にも排除されていた中世、狂った⼈間を⾈に乗せて送り出した「阿呆船」が⽣まれた15世紀、狂⼈を動物のように扱った18世紀を紹介している。社会から排斥された「狂気」を⽬の当たりにするとき、私たちは、過去の⼈類の野蛮さを嘆く。
⼀⽅でAIを使って画像を作るとき、「⼿」がうまく⽣成できない問題が往々にして課題になる。⼿以外は良いのに、と嘆くAI画像の⽣成愛好家は多い。
この課題に対応するとき、ネガティブプロンプトにugly hand(醜い⼿)などと記載したり、⼿の部分のみを修正するAIで再学習したりして、「正常化」させる。
この作品においてはわざと⼿が5本指にならないように学習させていく⼿法で制作をした。AIに対して、「惜しい」という感想を持った時、無意識に排斥している⼈たちがいないだろうか。
AIへの指摘は私たちの無意識下にある狂気を逆照射し、狭い了⾒で世界を識別した気になり、安易な進歩主義に陶酔しながら本質的な部分で同じことを繰り返す「私たち」を暴露する。
written by 窪田望
素材 ⽣成AI、⼤判印刷、メディウム⼿彩
展⽰作品②:Self-Confessed-Critic
(丹原
健翔
・窪田望共同制作)

美術批評の中で登場する大袈裟で冗⾧な批評の言葉をAIに学習させ会場中に批評の文字が生成され続け、白い紙に文字が書かれ続ける。
AIのモデルはメガギャラリーから学習し、生成している。作品は不在で、批評の言葉だけが存在しているが、これはいわばドーナッツの穴を楽しむためのドーナッツである。
作品において最も重要なものがコンセプトだとした場合、ドーナッツの可食部の部分は脱着可能な装飾・メディウムであるはずだが、ドーナツの穴をつくるためには、ドーナッツの可食部分を作らざるを得ない。ドーナツを美味しいと言っている間に、ドーナツの穴を見失ってしまうかもしれないが、果たして、現代アートを鑑賞する鑑賞者にとって作品とは作品そのものなのか、それともキュレーションされたテキストによるものなのか。作品と批評、内実と演出の関係性はどうあるべきなのか。その認識に揺さぶりをかける。
written by 窪田望

展⽰作品③:⾰命の夢 (制作:窪田望)

作家名 窪⽥望
素材 映像、⽣成AI、グラニュラー合成
制作年 2024
この映像作品は、フィリップ・K・ディックのSF⼩説《アンドロイドは電気⽺の夢を⾒るか?》に触発された作品であり、現代の⼈⼯知能(AI)と⼈間の関係性に焦点を当てている。ディックの物語では、アンドロイドが⼈間と区別できないほどに⼈間に近い存在として描かれている。この映像は、AIによって構成された画像を束ね、動画化した上で、フランスの⼈権宣⾔を読み上げたナレーションが流れている。このナレーションもAIで作られており、AIと⼈の境界線を曖昧にしている。フランス⼈権宣⾔の定義する⼈間は、無意識の前提として男性のことであり、⼥性は含まれていなかった。1791年9⽉にはオランプ=ド=グージュが発表した『⼥性および⼥性市⺠の権利宣⾔」では、権利の主体を⼈(homme)としているのに対して⼥性(femme)とし、市⺠(citoyen)としているところを⼥性市⺠(citoyenne)と書き改め、同じように前⽂と17条から成っており対応させた。
問うべきはこの「無意識の前提」は現在においても起きていないかという問題である。オックスフォード⼤学のカール・フレイ博⼠とマイケル・オズボーン准教授が執筆した論⽂では、AIの導⼊により9割以上の確率で無くなると考えられる仕事が紹介され、AIは⼈の仕事を奪うのか、という議論は今もよく語られるようになった。また、その危険性をコントロールするべきという指摘も多く、2024年5⽉21⽇(現地時間)、欧州連合(EU)において「AI法(Artificial Intelligence Act)」が成⽴した。
AIを抑えつけ、コントロール可能にしようとしている姿は産業⾰命の時のラッダイト運動にも、アウシュビッツ収容におけるユダヤ⼈迫害とガザ地域の問題にも重なるかもしれない。私は、モデルマイノリティの議論から随分離れたAIの世界から、AIと⼈類が⼆項対⽴する構造そのものに警鐘を鳴らす。
written by 窪田望